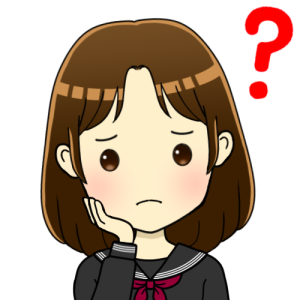
「撮った写真に緑の光が写ってるんだけど、これって何?」
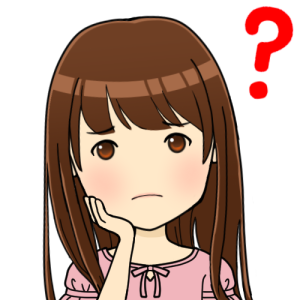
「もしかして、心霊現象……!?」
そんな疑問にお答えします。
1)写真の緑の光の正体はなに?逆光?
2)緑の光が映るスピリチュアルの意味
3)緑の光が写った時の注意点はある?
4)写ってしまった緑の光を消す方法は?
5)事前に防ぐ方法
旅行や散歩等で素敵な景色と遭遇し、写真を1枚……なんてことは珍しいことではないでしょう。
そんなとき、改めて見た写真に緑の光が浮かんでいたらゾッとしてしまいますよね。

もしかして心霊現象かも、と思ってしまうのも不思議ではありません。
結論から申し上げますと、心霊現象ではなく光の反射による現象です。
しかしこれだけでは面白くないので、スピリチュアル的な意味も含め、以下で詳しく解説していきます。
光りを発生させない方法についても述べていくので、ぜひ最後までご覧ください。
1)写真の緑の光の正体はなに?逆光?
写真に写る緑の光は、写真用語で「ゴースト」と言います。
(フレア又はオーブとも呼ばれることがある)
霊的な雰囲気が醸し出されていますが、残念ながら(?)心霊現象ではありません。
この正体は、光源とレンズの反射を要因として起こる科学的な現象です。
詳しく言うと、「光源からの光がレンズ内で再反射し、それによって光源の対称の位置に光の像が現れる」ということ。
緑色になるのは、その色が持つ波長の特性によるものだそうですよ。
2)緑の光が映るスピリチュアルの意味
科学的な現象とはいえ、スピリチュアル的な雰囲気も感じますよね。
そういった観点から見ると、緑の光はどのような意味を持つのでしょうか。
端的に申し上げると、「幸福」の象徴です。
基本的には良い意味のものなのでご安心ください。
今回はその中から3つ紹介していきます。
①守護霊、精霊等から守られている
写真を撮ったスポットが精霊に護られていることを示しています。
ちなみに神社だった場合は神聖な場所であるという印だそうです。
また、祀られている神様からメッセージが送られている可能性もあります。
②自然と繋がっている
緑は自然界に満ちている色です。
つまり、あなたと自然との繋がりを表しており、自然からのエネルギーを受け取れていることを示しています。
それ自体に癒しの効果を持っているので、写真を見ながら深呼吸するだけでも良いという話も……。
③幸運の到来、新たな出発への予兆
緑の光には「幸運」という意味があります。
また、あなたの身に良い意味で変化が起こることを予告しているのかもしれません。
信じるか信じないかは別として、何か心当たりがある場合はそれに向けて準備を進めてみてはいかがでしょうか。
結果的に幸運を呼び寄せることになるかもしれませんよ?
3)緑の光が写った時の注意点はある?
基本的には良い意味を持つ緑色の光ですが、場合によっては注意が必要です。
というのも緑色には「回復」という意味もあり、ひいてはあなたの心身が疲弊していることを伝えてくれているのかもしれません。
自覚のないまま疲れが溜まり、倒れてしまっては大変です。
このサインをきっかけに、最近きちんと休めているかどうか立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。
4)写ってしまった緑の光を消す方法は?
スピリチュアル的な意味を解説してきましたが、残念ながら写ってしまったものが急に消えるということは考えにくいでしょう。
そのため、光を消す方法としては正攻法の「レタッチ」を駆使するのがオススメです。
レタッチ用のアプリやソフトは無料のものがいくつもありますし、光以外のものを消せるので、1つ用意しておくと便利です。
またGoogleピクセルなどでは「消しゴムマジック」が標準装備されているので、それを使ってみるのも良いですね。
5)事前に防ぐ方法
ここからは、最初から緑の光を写さないようにする方法を2つ紹介していきます。
①光源をフレームの中心に配置する
緑の光(=ゴースト)は光源の対角点に発生します。
そのため、フレームの端に光源があると現れやすくなってしまうのです。
光源を含めた写真を撮りたい場合は、中央に配置した構図になるよう調整してみてください。
②フレーム内に光源を入れない
最初から光源を入れなければ、より簡単に解決します。
光源がある方角だとしても、ズームをしてフレーム外に追いやってしまうなど調節してみましょう。
また、角度を変えたり光源を建物等で隠したりすることで、光源がフレーム内にあっても光を発生させないようにするという方法もあります。
その時々によって状況や条件は変わってきますが、試行錯誤していくうちに何となくの傾向をつかめるようになっていくかもしれません。
まとめ

今回は、写真に写る緑の光の謎について解説していきました。
科学的側面/スピリチュアル的側面からみていきましたが、いずれにしてもそこまで恐れることではないですし、撮り方を工夫すれば発生させないようにすることも可能です。
写真を撮る際に、ぜひお役立ていただければと思います。

コメント