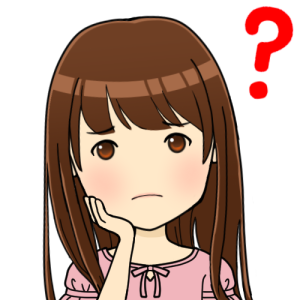
「大人がぬいぐるみ症候群になる理由や心理が知りたい」
あなた自身、大事にしているぬいぐるみはありますか?
中には、四六時中ずっと持ち歩いていたり、手放せなくなっていたりする人もいるかもしれません。
ぬいぐるみを手放せない大人とはどのような人でしょうか。
周囲の人々や、自分自身の心や身体に不調が起きていないか、一緒に確認していきましょう。
1.【ぬいぐるみ症候群】大人がぬいぐるみを手放せない理由3つ
大人になってもぬいぐるみが手放せない理由は人それぞれあると思いますが、代表的なものを3つ挙げるとすればこのようなものになるでしょう。
・小さいころから捨てられず大切にしているものがある
・ストレスや不安があり癒しを求めて依存している
上記の二つは特に問題がないように思えます。
私自身、小さいころから一緒に過ごしているぬいぐるみがあり、家族の一員のような気持ちで捨てられません。
一方、ずっと一緒でないと不安を感じたり、生活に支障が出るほど落ち着かなくなったりする人もいます。
今回はそんな、「ストレスや不安があり癒しを求めて依存している」人について、原因や改善点を探っていきましょう。
2.そもそもぬいぐるみ症候群とは?原因や改善の仕方
・原因
・改善するには?
定義
ぬいぐるみ症候群とは、ぬいぐるみが身の回りにないと不安な気持ちになったり、落ち着かなかったりすることです。毛布やタオルなどが対象の人もいます。
この由来は、スヌーピーに登場するライナス君です。
彼は常にブランケットを持ち歩くことで安心感を抱いており、その様子から、ブランケット症候群とも呼ばれています。
原因
多くは小さな子どもに見られる症状です。生まれた直後はほとんどの時間を母親と過ごしますが、母親から離れて自立する際、母親の代わりとしてぬいぐるみや毛布に頼ることがあります。
このような症状は病気ではなく、ぬいぐるみなどは母親からの「移行対象」であるという風に医療業界では言われることもあります。
まれに大人になるまでこの症状が続く人や、大人になってから発症する人も存在し、対象はぬいぐるみだけでなく、恋愛やインターネットなどさまざまです。
大人になってから症状がみられる場合、人間関係や生活習慣、環境の変化など、不安やストレスから発症してしまう人が多いでしょう。
改善するには?
子どもにこのような症状がみられた場合には、無理に改善する必要はなく、見守ることが大切だと言われています。
しかし、大人になって症状がみられる人の中には、依存状態を改善したいと思う人もいるかもしれません。
ぬいぐるみ症候群を改善するには、依存対象を無理やり手放すのではなく、依存してしまう原因を探ることが大切です。
不安を緩和してくれているぬいぐるみを奪うことで、不安感や落ち着かない症状を悪化させてしまうことになりかねません。
不安やストレスを少しでも取り除き、精神的な安定を目指すことができれば、ぬいぐるみなどへの依存状態も自然と軽くなるでしょう。
3.ぬいぐるみ症候群かを確かめる質問4つ
ぬいぐるみに安心感を持つ人は多いと思いますが、それが過剰であったり、依存的であったりするかどうかは個人では判断しづらいですよね。判断材料として4つの質問があるので参考にしてみましょう。
・ぬいぐるみを常に持ち歩いている
・ぬいぐるみがないと不安になる
・ぬいぐるみの前だけではありのままの姿でいられる
・ぬいぐるみに癒されることが多い
1つずつチェックしていきます。
・ぬいぐるみを常に持ち歩いている
家にいるときも、外出しているときも肌身離さず、ずっと持ち歩いていたり、握ったりしていませんか?
・ぬいぐるみがないと不安になる
少しの外出でも、ぬいぐるみがないと落ち着かないなどで持ち出したりしていませんか?
・ぬいぐるみの前だけではありのままの姿でいられる
相談相手になっていたり、素の自分を出していたりなど、リラックスした状態でいられる人もいるでしょう。
本当にリラックスした状態はご家族や友人にも見せず、ぬいぐるみのみですか?
・ぬいぐるみに癒されることが多い
一緒にいることで安心し、疲れが取れるような気持ちになりますか?
ぬいぐるみから少しでも離れた時、生活に支障が出るほど不安定な精神状態になる場合、ぬいぐるみ症候群の可能性が高いです。
すべてに当てはまる方は、自分の生活環境を振り返ってみましょう。
しかし、一つや二つ当てはまるからと言って、必ずしもぬいぐるみ症候群というわけではありません。
実際に、ぬいぐるみは癒し効果があると言われています。
4.ぬいぐるみと触れ合う効果やメリット
病院などでは、セラピーや治療法として、ぬいぐるみの癒し効果を利用されることがあります。
人と触れ合うことで分泌されるオキシトシンは、幸せホルモンとして有名ですが、ぬいぐるみに触ったり抱きしめたりすることでも分泌されることがわかっています。
また、話しかけることでストレス解消や気持ちの整理にもつながりますし、孤独感も緩和できます。
ぬいぐるみと一緒に寝ることで安眠でき、不眠症や不安からの寝つきの悪さを軽減できる人もいるでしょう。
このように、ぬいぐるみと接することで得られるメリットはたくさんあるのです。日々の生活の中でリラックスやリフレッシュの一環としてぬいぐるみを用いることも効果的でしょう。
しかし、ぬいぐるみがないと不安になるほど依存的になってしまった場合、それほどまでにストレスを感じさせているものの原因を探らなければいけません。
程よい距離感を保てるのであれば、ぬいぐるみに頼っていることが必ずしも悪いというわけではない理由がお判りいただけたでしょう。
まとめ
・改善するには、不安やストレスの原因を探り、取り除く必要がある
・ぬいぐるみなどには科学的に癒し効果があるとされており、ストレス軽減のために意図的に使用することもできる
ストレスの多い現代社会ですが、ぬいぐるみだけではなく、アルコールや薬など、何かに依存的になってしまうことは健康的ではありません。
心身に不調があると感じた場合にすぐに対応できるよう、いつでも生活環境を変えられるようにいくらか貯金を用意したり、
相談相手を決めていたりなど、普段から逃げの場を用意することが大切になるのではないかと思います。

コメント