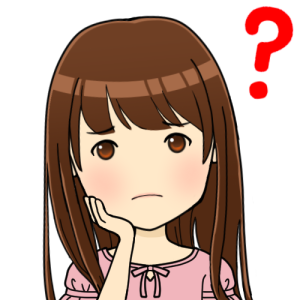
「おにぎらずの痛みにくい具が知りたい。」
そんな疑問を解消します。
1.【おにぎらず】の傷みにくい具10選!
2.傷みにくい具材の特徴
3.傷みにくい作り方のポイントは?
4.外出時に持ち運ぶ際に気をつけること

結論から言うと味が濃い目のものやしっかり加熱してあるもの
などが痛みにくい具材といえます。
痛みにくいおススメの具や作り方のポイントもご紹介します。
ではご覧ください。
1.【おにぎらず】の傷みにくい具10選!
〖おにぎらず〗とはその名のとおり、握るのではなく
海苔の上にご飯と具材をのせ、挟んで作るおにぎりのことです。

手が汚れることもないですし、
食べやすいと評判なんです。
そんなおにぎらずは具材も自由自在。
だからこそ痛みにくい具材には気を付けたいところです。
そこで痛みにくい具を10選ご紹介します。
①唐揚げ
お弁当のおかずと言えばコレという人も多いのでは。

そんな人気の高い唐揚げはおにぎらずにも最適ですよ。
ボリュームも満点ですね。
ポイントは菌をおさえる効果が期待できる、からしを追加すると
殺菌効果も期待できます。
②スパム
スパムと卵焼きを挟んだいわゆる沖縄のソールフードと言えば
行列が出来る人気店が有名ですね。

スパムと卵焼きに加えお好きな具材で自分風にアレンジして
オリジナルポーたま風を作ってみてはいかがでしょうか。
③とんかつ・チキンカツ
カツ類はご飯との相性もバッチリでボリュームもあり
おにぎらずの具としておススメですよ。
中でもとんかつやチキンカツならば、抗菌作用が期待できる
大葉や梅肉などとの相性も良いので痛みにくさの面でも
最適ですね。
④きんぴらごぼう
野菜を摂りたい方にはきんぴらごぼうがおススメです。
野菜類は生のものよりもしっかり加熱したものの方が
痛みにくいです。

そこでちょっと濃いめに味付けしたきんぴらごぼうなら
満足感も得られ野菜も摂れますね。
⑤やっぱり定番(鮭・たらこ・梅)
おにぎりの定番と言えば鮭・たらこ・梅ですよね。
おにぎらずでもやっぱり食べたい定番の具。
その中でも鮭は焼き鮭の他にも、鮭フレークなどを使えば
手間もかからず簡単に出来てしまいますね。
⑥焼肉
焼肉もやはりはずせません。
お好きなタレで味付けができるところも良いですね。

野菜も一緒に炒めたら栄養バランスも
いう事なしです。
⑦たまご
卵はそれ単体でも主役になり得ますし
他の具材の引き立て役としても大活躍ですね。
卵を使う際の注意点としては中までしっかり加熱をすることです。
⑧ツナ
筆者も大好物のツナのおにぎり。
おにぎらずとしても活躍してくれること間違いなしです。
ツナ缶の油はしっかりきることが
傷みにくくするポイントですよ。
⑨韓国風

ビビンバやキンパといった韓国風の具材を使っても
美味しいおにぎらずが出来上がります。
韓国海苔が無い場合でも、
薄めにごま油+塩を塗ることで韓国風海苔に変身しちゃいますよ。
⑩そぼろ
そぼろは鶏でも牛でも豚でも合い挽き肉でも
それぞれ色々なレシピが楽しめますよ。
甘辛い味付けで卵と一緒に挟むのもよし、
サルサソースとまぜてタコス風にアレンジしてもOK
など複数の味を楽しめる優秀な具材ですね。
2.傷みにくい具材の特徴
傷みにくい具材の特徴としては、
スパムやベーコンなどそれ自体の塩分の濃いものや
きんぴらごぼうや焼肉等のように調味料で
しっかり味付けをしてあることがあげられます。

また卵はおにぎらずにもかかせない具材ですが
半熟など加熱が不十分だと傷みやすくなります。
ポイントはしっかり中まで加熱することです。
ゆで卵を作る時は黄身までしっかり火を通しましょう。
さらに揚げ物全般は傷みにくい具材といえます。
3.傷みにくい作り方のポイントは?
作り方で傷みにくくするには
ご飯も具も冷ましてから包むのがポイントです。
アツアツのご飯に調理したての具材を包んでしまうと
閉じ込められた蒸気が余分な水分となり傷みやすくなってしまうのです。

そんな事態を避けるためにも
ご飯と具材はできるだけ熱をとってから調理してみてください。
もう一つのポイントは
素手では触れないことが大切です。
素手でさわった具などの菌が時間の経過にともなって
繁殖しかねないためです。
折角の握らないおにぎりですから、
菜箸やラップを徹底活用しましょう。
4.外出時に持ち運ぶ際に気をつけること
外出時に持ち運ぶならば保冷剤と保冷バッグを使用するのは
鉄則です。
おにぎらずをそのまま持ち歩くことで細菌が繁殖し、
食中毒などを引き起こしかねません。

細菌の増殖条件には温度や湿度が関係していることから
保冷剤と保冷バッグのダブル使いで
細菌の繁殖をブロックすることが効果的といえるでしょう。
またそれほど気温が高くない場合、長い時間持ち歩かない場合なども
油断は禁物です。
少なくとも持ち歩く時は保冷剤の使用はしておいた方が
安心ですよ。
5.まとめ
今回の記事ではおにぎらずの傷みにくい具やその特徴について
ご紹介しました。

外出時の持ち運びで注意することは
傷みにくいポイントさえおさえてしまえば
バラエティ豊富なおにぎらずを楽しむことができます。
以上、【おにぎらず】の傷みにくい具10選!について
ご紹介しました。

コメント